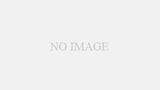現代の情報の洪水の中で、(しかしその大量の情報の大半は反復でしかないのだけれども)、
人は自分の見たいものしか見なくなったと嘆きが聞こえる。
たしかにそれはそうで、昔は、専門分野とは言っても限られた情報しかなく、
時間もあるので、自ずと、自分の専門の周辺分野まで、目を通し、話を聞くことになったものだ。
その中でまた、独自の成果も得られたものだろう。
しかし現代では、論文検索によってヒットする専門論文は極めて多く、
それらが、どの程度無意味な反復でしかないのかを確認するために、
多くの時間を要するようになった。
時間をかけているのに、大した論文はないことが確認できたというだけである。
現代の学者は論文を量産しないといけないので、反復をいとわず、書く。
本人は、細分化した専門領域の中で生きているから、それは反復ではなく、
新しい論点を提出したものだと考えている。
顕微鏡で見れば、違いはあるが、肉眼では、大した違いはないようなものだ。
それでは、もっと広範な分野に渡り、勉学を極めればよいのだろうか。
それは実際は無理というもので、あまり成果は得られない。浅くなる。
素人論議の少し上等な程度のものになる。
しかしながら、現代の情報消費者の大半はその程度の論議を好むので、
ちょうどよいとも言える。
自分に判別できる範囲のものを懸命に追いかけていると、
自分の見たいものしか見ないと批判されるのだろう。
全く考えの違う人と対話するのも大変疲れる。
ある程度、共通の前提が必要だ。
しかし、その、ある程度の共通の前提を要求した途端に、
専門家同士の些末な議論と言われるようになる。
誰が判定するのか、それが問題だ。
大学の論文の判定は、他分野の教授が関わったりする。分かるわけがない。
自分の教室の教授でさえ、弟子の論文の内容がわかるとは限らない。
分かると言い張るなら、凡庸な弟子しか育ててこなかったということだ。
論文のインパクトファクターなどは、こうした状況では、仕方のない必要悪と言えるだろう。
情報の洪水の中で、人は見たいものしか見ない
 未分類
未分類